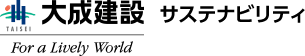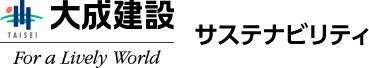- HOME
- トップコミットメント
※このページは、大成建設グループ統合レポート2023に掲載された内容です。
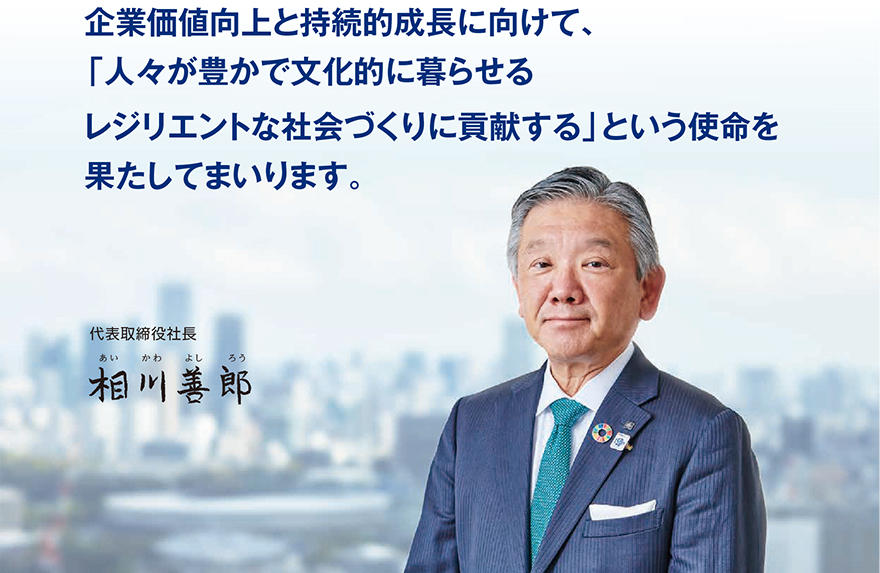

はじめに
先般、当社が施工中の工事において鉄骨建方等の精度不良事案及び工程遅延事案を発生させてしまいましたことを、改めてお詫び申し上げます。それぞれの事案により失った信頼を取り戻すためには、並々ならぬ努力が必要であり、大変厳しい道のりになると考えております。
この難局を乗り越え、新たな成長につなげるためには、「人々が豊かで文化的に暮らせるレジリエントな社会づくりに貢献する」という当社グループの使命のもとに全役職員が志を一つにし、品質・工程・安全という基本を大切にして、誠実に日々の業務に取り組まなければなりません。そして、お客様の期待と想像を超える価値と満足と感動を提供し続け、企業活動を通じて社会課題を解決していくことが重要となります。
私は社長としてその先頭に立ち、信頼の回復に全力を尽くしてまいります。
中期経営計画(2021-2023)の進捗状況
建設投資は、底堅い公共投資とコロナ後を見据えた製造業を中心とした旺盛な民間設備投資に牽引され、コロナ前を上回る水準まで持ち直しつつあります。しかしながら、建設資材価格が幅広い品目で高騰したことが工事の損益に甚大な影響をもたらしており、当社グループを取り巻く経営環境は非常に厳しい状況となっております。
このような状況のもと、中期経営計画(2021-2023)の2年目にあたる2022年度業績は、期首手持工事残高が順調に進捗したこと等から、グループ売上高は増収となりましたが、損益に関しましては、前述の鉄骨建方等の精度不良に対する是正工事関連費用の計上や建設資材価格の高騰の影響を受けた建築事業の利益率低下により、営業利益をはじめとする各段階利益は前年度実績を下回る結果となりました。
中期経営計画最終年度である2023年度の業績見通しにつきましては、グループ売上高、営業利益、純利益共に中期経営計画に対して未達となる見通しです。
営業利益の未達要因としては、主に次の3点です。初めに「生産体制の整備の遅れ」です。現中期経営計画は、一定の利益が確保できることを前提に事業量の拡大による利益額の積み増しを目論んでおりましたが、期待した生産性の向上と要員の確保がかないませんでした。次に「複数の低採算大型工事の影響」です。案件の大型化に伴い競争が激化したことにより低採算で受注した複数の案件が利益を押し下げました。最後に「高騰した建設資材価格に対する価格転嫁の遅れ」です。施工者選定から着工までに時間を要する設計施工案件での資材価格高騰分及び一部グループ会社での原油価格高騰分の価格転嫁が進まず、利益率が低下しました。
これらの未達要因を踏まえ、次期中期経営計画に先立ち、今年度より次の施策に取り組んでおります。初めに「適正な事業量の確保と生産体制の立て直し」です。社員の労働環境を踏まえ、施工量と利益のバランスを見極めながら事業を進めていきます。次に、東京オリンピック後の競争激化による採算低下を踏まえ、「利益重視主義」を再徹底し、受注時審査の厳格適用、重点分野への要員配置などを行います。最後に、物価高騰分の価格転嫁交渉を粘り強く継続し、利益回復を図ってまいります。
企業価値向上と持続的成長に向けて
当社グループは、これまでに幾度も困難な状況を経験してきましたが、その度に、役職員が一丸となり力を結集して困難を乗り越え、次の成長につなげてきました。大変厳しい状況に置かれている今こそ、先人から受け継いだ「困難をチャンスに変えるDNA」を活かして、失敗を糧に将来の成長につながる挑戦をしなければなりません。私は、率先して行動するとともに、役職員が安心してチャレンジできる環境を整えていきます。
当社グループのさらなる成長に向けて、建設事業における大切な土台は「品質・工程・安全」であり、重要な課題は「持続的成長に向けた事業基盤の構築」と「人的資本の充実」であると考えています。以下、その詳細についてご説明します。
1. 品質・工程・安全
~技術者としての矜持を持ち誠実に取り組む~
建設業を中核とした事業活動を通じて社会資本づくりを担っている当社グループにとって、品質・工程・安全は基本であり、成長の土台となるものです。
当社グループが手掛けるプロジェクトは、人々の生活を支える重要な社会インフラであり、多くの人に信頼されて初めてビジネスが成り立ちます。建設工事に携わる全ての役職員が、ものづくりの伝統を継承しながら社会に貢献する技術者として、基本の重要性を再確認し、矜持を持って誠実に業務に取り組んでまいります。そして、それを一つずつ着実に積み重ねていくことにより、お客様と社会からの信頼につなげ、成長のための土台をより強固なものにしていきたいと考えております。
品質につきましては、現在、全社をあげて、コンプライアンスの再徹底及び品質管理プロセスを確実に機能させる仕組みの強化等に取り組んでいます。全役職員が、もう一度「TAISEI QUALITY ~品質は私たちのプライド~」という原点に立ち返り、適正な品質管理を実施してまいります。
工程につきましては、本社・支店による作業所巡視の頻度を高める等により、各工事の進捗状況および課題を本社・支店・作業所で共有し、作業所へのバックアップ体制を万全にして、確実な工程管理を行ってまいります。
安全につきましては、「安全第一主義」のもと、中期経営計画(2021-2023)の重点課題の一つに「死亡災害ゼロ、重大災害ゼロ」を掲げ、当社グループの事業に携わる全ての人が安心して働くことができる作業環境を築くために、安全衛生管理の向上に努めています。2022年の当社単体の度数率(災害発生の頻度を表す数値)は0.31となり、ここ10年で半分以下に改善されています。今後も、気を緩めることなく真摯に安全衛生管理に向き合い、安全第一主義を徹底してまいります。
2. 持続的成長に向けた事業基盤の構築
~お客様の期待と想像を超える~
1. レジリエントな社会づくりに貢献する事業の推進
当社グループがさらなる成長に向けて進むべき道は、CDE3(建設、開発、エンジニアリング、エネルギー、環境)の各分野において、中長期的な視点を持ってリソースを投入し、技術や事業に磨きをかけ、お客様の期待と想像を超える価値と満足と感動を提供し続けることです。そして、さらに多くのステークホルダーの幸福の増大に寄与することによって、社会貢献を果たしていくことです。これらを追求し続けることが、当社グループの企業価値の向上と持続的成長につながると考えています。
CDE3のうち、当社グループの核となる建築・土木の建設事業については、いかなる工事においても、お客様の満足と感動はもとより社会への貢献という熱い使命感を持って取り組んでいくことが重要です。品質・工程・安全という基本を徹底しつつ、DXによる生産システムの変革を進めるとともに、環境・社会課題の解決に向けた革新的な技術開発を進めて、競争優位性を高めていきます。併せて、お客様の期待と想像を超える提案をするために、設計力及び提案力の向上にも取り組んでまいります。海外建設事業については、重点国・地域において、現地に根差して確実に利益を上げる体制の構築に努めています。
開発事業とエンジニアリング事業については、当社グループの成長エンジンと位置付けています。開発事業については、不動産ポートフォリオの最適化と投資効率の追求による安定的な収益基盤の構築、エンジニアリング事業については、医薬品分野や食品分野等で培った強みを生かし、事業領域の拡大に向けた取り組みを進めています。いずれの分野においても、当社グループの総合力を最大限に生かして、成長を加速させたいと考えています。
エネルギーと環境については、環境分野のフロントランナーを目指し、カーボンニュートラル・サーキュラーエコノミー・ネイチャーポジティブや再生可能エネルギー等について、組織を整備して取り組みを進めています。
全ての分野において、レジリエントな社会づくりに貢献するために重要となる考え方が、CSV(Creating Shared Value:共通価値の創造)、すなわち企業活動を通じて社会課題を解決することです。社会価値と企業価値の両立という観点においては、当社グループは、社会インフラの構築を通じて深く社会に貢献することができます。私たちが提供する社会インフラは50年、100年という長い時間を生き続けます。今後は、時代の先を見据えて、創り出す構造物に社会価値を付加し、事業化していくことによりCSVを実践してまいります。
2. 持続可能な環境配慮型社会の実現と地域連携の推進
社会課題の解決への貢献において、特に重要となる分野は「持続可能な環境配慮型社会の実現」及び「地域連携の推進」であると考えています。
当社グループは、本年3月に環境方針及びグループ長期環境目標を改定し、持続可能な環境配慮型社会の実現に向けて、カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー、ネイチャーポジティブをキーワードとして、それぞれの実現・深化を目標に掲げ、事業を通じて社会に貢献することを目指しています。
特に、カーボンニュートラルに関しては、スコープ1・2に加えて、スコープ3(サプライチェーン)のCO2排出量ゼロを2050年目標としており、幅の広いZEB技術(新築ZEB、グリーン・リニューアルZEB、ZEF、ZEH、ZEH-M)をはじめ、環境配慮コンクリート「T-eConcrete®」やCO2排出量を削減した鋼材などの開発・普及に一層注力していきます。また、建築物のライフサイクルのCO2排出量実質ゼロを目指す「T-ZCB®(ゼロカーボンビル)」についても実証を開始しており、今後、調達フェーズにおける「ゼロカーボン・デザイン」、施工フェーズにおける「ゼロカーボン・コンストラクション」、運用フェーズにおける「ゼロカーボン・オペレーション」という、それぞれの段階における脱炭素技術に磨きをかけていきます。
地域連携については、人口の減少と超高齢化社会の到来という課題に直面する中、国・地方自治体は各地域が特徴を活かして自律的で持続可能な社会を創生できるよう様々な取り組みを進めており、企業としても、地域と連携して課題を解決し、地域活性化に貢献することは重要な責務となります。建設事業を礎として、エンジニアリング技術や環境関連技術等の当社グループの総合力を活かし、中長期的な視点を持って地域に寄り添い、協働して課題解決に取り組んでいきたいと考えています。
社会に対してインパクトのある貢献をしながら利益を出すことは容易なことではありません。しかし、難しいからこそ、実現できれば、簡単には真似のできない強みとなり、当社グループの競争優位にもつながります。本年4月に地域連携のための新たな社内推進体制を始動させており、今後、異業種との連携も図りながら注力してまいります。
3. オープンイノベーションの加速
当社グループの競争優位の源泉は技術力です。世の中の技術の進歩は、私たちの想像よりも早く、かつ非連続的に変化しており、前例主義・自前主義で取り組んでいては、この変化のスピードに対応できません。同業や周辺業種だけでなく、むしろ異業種と当社の知恵を掛け合わせて融合させることでイノベーションが生まれます。
長年に渡るものづくりの伝承の中で培われてきた建設生産プロセス、ファシリティマネジメント、脱炭素等に関する幅広い技術・ノウハウを絶えずブラッシュアップし、より高みを目指す当社グループ社員のマインドは業界随一だと自負しています。優れた技術・ノウハウと熱いマインドを両輪に社会に向き合い、多くの人が気づいていない潜在的なニーズを捉え、志を共有できる異業種のパートナーと協働してオープンイノベーションを加速させ、お客様に満足と感動をしていただける新たな価値を創造してまいります。
4. サプライチェーン全体での取り組み
当社グループにとって、専門工事業者及びサプライヤーは、お客様の期待と想像を超える仕事を成し遂げるための大切なパートナーであり、事業を通じて社会課題を解決しながら共存共栄していく仲間です。基幹協力会社の集まりである倉友会及び全ての協力会社が参加する安全衛生環境協力会との連携を強化し、「人々が豊かで文化的に暮らせるレジリエントな社会づくりに貢献する」という当社グループの使命への共感を深めていただき、サプライチェーン全体での取り組みを進めてまいります。
今、建設業界は、「担い手不足と就業者の高齢化」及び「2024年4月からの時間外労働上限規制適用」という大きな課題に直面しています。日本建設業連合会の一員として業界全体での取り組みを強力に推し進めつつ、倉友会及び安全衛生環境協力会と協働して知恵を出し合い、長時間労働の是正と休日の作業所閉所はもとより、建設技能労働者の処遇改善等に努め、魅力的な労働環境を提供してまいります。
3. 人的資本の充実
~当社グループの未来へ投資する~
1. 社員の働きがいとエンゲージメントの向上
当社グループの使命を果たすためには、まずは当社グループで働く社員とその家族が十分に幸福であることが絶対条件となります。社員とその家族が幸福であるためには、会社が社員一人ひとりを理解し、各々が個性や強みを最大限に発揮できる場を提供することにより、社員一人ひとりが会社を信頼して、目指す姿の達成に向けて自発的・主体的に貢献する意欲を持つことが重要となります。
会社と社員が強いエンゲージメントで結ばれているからこそ、社員が持てる力を存分に発揮して、お客様の期待と想像を超える価値をお届けすることができます。この意味において、社員はまさに「人財」であり、当社グループの企業価値を向上させるエンジンは社員一人ひとりの「働きがい」にあると言えます。そして、全ての社員がいきいきと働くことができる環境を構築することは、社長である私の最も重要な使命の一つであります。
昨年度、当社及び主要グループ会社の社員を対象に、外部コンサルタントによるエンゲージメント調査を初めて実施しました。調査結果を真摯に受け止め、あるべき姿とのギャップを分析し、年齢・役職・組織など属性別に社員の働きがい向上につながる取り組みを進めています。
今後も、定期的に社員のエンゲージメントの状況を把握し、さらなる改善に努めていきます。そして、職場の心理的安全性を高め、社員が会社と仕事に誇りを持ち、ワクワクとしながら質の高い仕事による社会貢献ができる環境を創出してまいります。
2. 女性活躍推進及び人財の多様性確保
当社グループでは、かねてより専門組織を設けて、多様な人財が力を発揮することができる環境の整備に取り組み、特に女性活躍推進に力を入れてきました。女性技術者も増え、職位者として活躍する女性社員も少しずつ増えてきていますが、他業種と比べて、まだまだ改善の余地があります。社会が激しく変化しながら複雑化し、価値観が多様化している中、「日本人・男性・新卒(転職経験なし)」という同質的な集団であり続けることは、潜在的なリスクを抱えているといえます。この変化に対応しながらビジネスチャンスを掴み、持続的成長につなげるためにも、女性社員の活躍を一層推進するとともに、キャリア採用の充実、外国人財の登用等にも力を入れていきます。
また、当社は、女性活躍推進の環境づくりにもつながる取り組みとして、男性社員の育児休業取得に注力してきました。会社をあげて取り組んだ結果、対象となる男性社員の取得率は2017年度以降連続して100%となっており、平均取得日数は11.6日(2023年3月現在)となっています。今後は、100%取得を継続するとともに平均取得日数の増加に取り組んでいきます。
私は、「社員が安心して結婚・出産・子育てできる会社」を目指しています。これを実現し、多様な人財がいきいきと働いて、多角的な視点で社会とお客様のニーズを捉え、質の高い仕事を成し遂げられるよう環境整備に取り組んでまいります。
3. 人財育成の推進
人財育成については、当社グループの未来への投資であると捉えています。社員の育成にあたっては、単に技術力のみならず、全人格的な育成が為されるように力を注いでいく方針です。変化が激しく、不確実性と複雑性が増して将来の予測が困難である今の時代においてビジネスを成功させるためには、論理性に加えて、豊かな感性と構想力・創造性が必要です。それを磨くためには、リベラルアーツの習得が欠かせません。また、正解のない世の中においては、ビジネスの大前提となる「フェアプレーの精神」が一層重要になります。社員が自分の業務だけでなく、様々な知識とリベラルアーツを習得しながら自らを磨き品格を高めて、より誠実に質の高い仕事ができるよう、そして、より豊かな人生を謳歌できるよう後押ししてまいります。
また、優れた成果をあげた事業等を対象とした社内表彰制度を設けていますが、これに加えて、一昨年より「TAISEI VISION 2030賞」を創設し、当社が目指す姿を実現するための優れた行動(たとえ目立たなくとも会社に大きく貢献する事業、果敢なリスクチャレンジや創意工夫の意識を持った業務遂行、会社の信頼構築に寄与する社会貢献活動など)に対し、その頑張りをタイムリーに表彰するよう努めています。この制度により、社員のエンゲージメントやモチベーションが高まり、自らを磨きながらより質の高い仕事にチャレンジする、という好循環が生まれることを期待しています。
さらに、昨年、若手・中堅社員による「TAISEI 次世代VISION 提案ワーキンググループ」を立ち上げ、【TAISEI VISION 2030】の達成に向けて当社グループが取り組むべき事項を提言してもらいました。若い世代の感性と率直な意見を経営に活かすとともに、今後も、引き続きマテリアリティの改定や次期中期経営計画の策定にも関わってもらうなど、次世代を担う人財の育成と意識向上にも力を入れていきたいと考えています。
将来の経営者候補の育成については、選抜した社員が経営会議にオブザーバー参加し、経営判断に関する生の議論を共有するとともに、社外取締役との意見交換会を実施する等により、当社の各事業の状況、経営戦略、及びコーポレートガバナンス等に関する見識を高める取り組みを始めました。さらに、対象者には、より高い意識を持ってリベラルアーツ習得に励み、真・善・美に関する感性を磨いていくことも求めています。今後も、当社グループの持続的成長に向けて、次世代の経営人財の育成を計画的に実施してまいります。
結びに ~創業150周年をさらなる飛躍へのスタートの年に~
今年、当社グループは創業150周年の節目を迎えました。これは、ひとえに先人たちの弛まぬ努力を、お客様をはじめとするステークホルダーの皆様に評価していただき、当社グループに信頼を寄せていただいた賜物であると、心から感謝申し上げます。これからも皆様との対話を重視しながら、持続的成長に向けた取り組みを進めてまいります。
創業者である大倉喜八郎は「時流を読む洞察力」「熟慮の上での勇気ある冒険心」「前例のないことに挑むパイオニア精神」を持ち合わせた人物でした。明治から昭和に至る激動の時代に先を見通して事業の道を歩み、前例のないことに果敢にチャレンジして、当社グループをはじめとする多彩な企業の設立・経営に携わり、事業を通じて近代日本の発展に大きく貢献しました。私たちは、この創業者の精神を受け継ぎ、「自由闊達」「価値創造」「伝統進化」という大成スピリットを大切にしています。
当社グループが大変厳しい局面にある今こそ、この大成スピリットを再確認して、150周年という節目の年が次の50年、100年先の未来に向けて飛躍するスタートの年となるよう、果敢にチャレンジすることが必要です。私たちが置かれている状況について正しい危機意識を持ち、「人々が豊かで文化的に暮らせるレジリエントな社会づくりに貢献する」という使命のもとに役職員一同全力を尽くして、“人がいきいきとする環境を創造する”というグループ理念を実現してまいります。
ステークホルダーの皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。